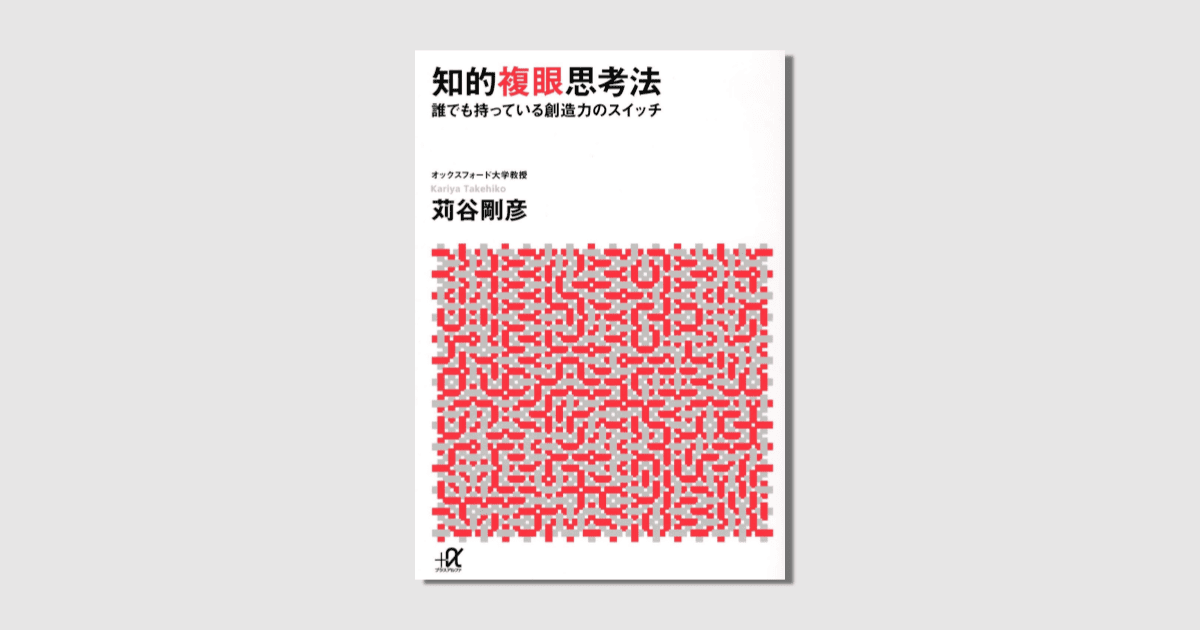“単眼”から“複眼”へ。多角的な視点で思考し、創造力をスイッチするための習慣
情報があふれ、価値観も多様化する現代、「ただ知識を詰める」「ただ答えを探す」だけでは思考停止に陥りがちです。
ビジネスの現場では、
- 一つの視点だけで立ち止まってしまう
- 常識と思われる枠組みに気づかず動いてしまう
- 自分の頭で「問いを立てる」「論理を組み立てる」機会が少ない
という悩みを抱える人が少なくありません。
この本は、そんな状況に対して、「視点を増やし、自分の頭で考える力」を取り戻すためのガイドです。
| タイトル | 知的複眼思考法 誰でも持っている創造力のスイッチ |
|---|---|
| 著者 | 苅谷 剛彦(かりや たけひこ) |
| 出版社 | 講談社 |
| 発売日 | 2002年5月20日 |
| ページ数 | 384ページ |
| 価格 | 968円(税込) |
| ジャンル | 思考法/自己啓発/ビジネススキル |
本書の概要
本書は、「複眼思考」という考え方をキーワードに、単なる知識や情報取得ではなく、物事を多角的に捉え、自分なりの論理で考え抜く力を鍛えるための実践書です。
構成としては、読書・文章作成・問いの立て方・視点の拡張といった流れで、思考の質を上げるための習慣が整理されています。
本書のポイント
特に印象に残ったポイント・要点
「知識を受ける」から「知識を創る」へ
本書では、読書や文章を書くことを通して、受け身の知識取得ではなく、自分の視点で知識を組み立て直すことを説いています。
この転換が、創造力・思考力のスイッチとなるという点が印象的です。
問いを立て、筋道を追う習慣
「なぜ?」と問いを立てる習慣、そして得られた情報を「どういう筋道で考えるか」を意識すること、
これが「複眼思考」のコアとして紹介されています。
常識に縛られない視点の拡張
単一の視点(=単眼)に依存せず、複数の視点から物事を捉えることで、“見えなかった真実”を捉える力が付くと説かれています。
読後の印象と実践へのヒント
この本を読み終えて感じたことは、「考えること」の質が、高速化・複雑化している今こそ、 思考の“枠”を広げる習慣が効果を発揮するということです。
実践ヒントとしては:
- 日常の読書/ニュース/記事に対して「この立場から見たらどうなるか?」と問いを投げかける
- 書くことで思考を整理する。短い文章でも「自分はこう考える/なぜそう考えるか」をまとめてみる
- 複数の意見や視点を並べて「どこが共通か」「どこが異なるか」を整理する
こうした習慣が、ビジネスの現場で求められる「自分で考える力」を育てます。
この本をおすすめしたい人
特に次のような方におすすめです。
- 情報があふれる環境で「自分なりの考え方を持ちたい」と感じている人
- ビジネスパーソン・ITエンジニア・メディア担当者で「思考力」「創造力」を高めたいと考えている人
- 他の人と同じ視点で動いていると感じていて、視野を広げたい人
一方で、すでに高度な論理思考や哲学的思考に慣れている方には、やや入門的と感じる可能性があります。
まとめ:視点を増やし、思考を深める習慣をつくる
本書『知的複眼思考法 誰でも持っている創造力のスイッチ』は、「自分の頭で考える」ための視点の拡張と習慣化を促す一冊です。
情報をただ受け取るだけの時代は終わり、多様な視点を持ち、問いを立て、筋道を追う――この“複眼”の思考スタイルが、創造的な働き方を支えます。
もし今、思考が停滞している、あるいは“他人の意見”だけで動いていると感じているなら、この本をきっかけに、思考のスイッチを入れてみてください。